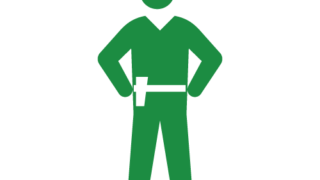こんにちは!枝林 志忠(しりん しただ)です!
当ブログでは、SF小説からクリエイターやビジネスマンに役立つような情報を
公開しています。
今回は、拡張現実と遺伝子をテーマにした藤井太洋『GeneMapper-full build-』を紹介します。
SF×農業ってあるの?
「SFと宇宙人」
「SFとロボット・機械」
「SFと宇宙」
「SFと理系」
「SFと工業」
・・・etc
これほどSFに関わるものがたくさんあってもう何を読めばいいのやら…。
そんな時、ふと思いました。
(あれ?そういえば『農業』をテーマにしたSF小説ってあまり見ないような…。)
まあ、実家が農家だからふと思ったという理由があったのですが…。
「スマート農業」があるのなら農業×SF小説があってもおかしくはないはずです。
農業の未来や食の安全について考えるためにも読んで損はないでしょう。

早速、調べてみることにしました。すると…。
『SFプロトタイピング:SFからイノベーションを生み出す新戦略』
(宮本道人監修・編著/ 難波優輝・大澤博隆編著)に農業×SFに関わる作品がありました。
それが藤井太洋『GeneMapper-full build-』という作品です。
以下、引用文です。
当初、Kindleにて出版されて話題を呼んだ、遺伝子×エンジニアリングSF。ゼロから遺伝子操作された作物がスタンダードとなった世界で、主人公の遺伝子デザイナーはテロリストの陰謀に巻き込まれる。プロたちはそれぞれのスキルでどう社会課題を解決するのか。科学技術への警告はあれど希望に満ちている物語のトーンは、SFプロトタイプの参考例として貴重なものだ。
引用:「SFプロトタイピング:SFからイノベーションを生み出す新戦略」
(宮本道人監修・編著/ 難波優輝・大澤博隆編著) より
(ほほう。遺伝子操作された作物ですか。)
Amazonのレビューを見てみますと、「遺伝子組み換え作物」「農業」といった言葉が出てましたので、購入して読んでみることにしました。
それでは、早速紹介していきたいと思います。
注目すべき点と作品の概要
注目すべき点
作品内で注目すべき点は、「遺伝子工学」です。
遺伝子工学とは、人の手で遺伝子を組み換える技術のことを言います。
遺伝子組み換え作物と聞けば、名前を聞いたことがあるという方も多いでしょう。

作品内では、「仮想現実(VR)」が扱われていることも特徴として挙げられますが、
今回は、農業分野特に遺伝子工学に焦点を当てて話していきます。
作品の概要
舞台は西暦2037年、遺伝子工学の発達によって、従来の遺伝子組み換え作物とは代わって
「蒸留作物」が食卓にのぼるようになった時代です。
主人公の林田は、遺伝子デザイナー「ジーン・マッパー(Gean Mapper)」という職業に就いています。
「ジーン・マッパ―」とは、遺伝子をマッピングするフリーランサーのことだそうです。
ある時、自身が設計した稲の遺伝子が崩壊したという話を聞き、原因究明にあたるため、
エージェントの黒川と共にベトナムを目指します。
そこで彼らが見たものとは…?
遺伝子技術の進歩、技術者に警鐘を促すような話になっています。
読後感じたこと
現在の技術との照合
現在では「蒸留作物」とは別の技術があると言えます。
「蒸留作物」は従来の遺伝子組み換え技術とは異なるもので、
- 従来の遺伝子組み換え→遺伝子の一部を組み換える・組み込む
- 蒸留作物→必要な遺伝子を残して補助的な要素を付け加える
上のような違いが見られます。
また、作品内で「蒸留作物」ができた理由は、稲に赤さび病が発生し東アジア飢饉が起きたため従来の稲が生産停止になったからだそうです。
本来、赤さび病は小麦に起きる病気なのですが、作品内では赤さび病を起こす糸状菌が突然変異を起こして、稲に発症する病気になってしまたんですね。
では、現在の遺伝子組み換え技術はどうなっているのでしょうか?
それに関して興味深い記事を最近見つけました。
以下、引用文です。
他の生物から新たに遺伝子を導入する遺伝子組み換えと異なり、遺伝子編集は作物自身の特定の遺伝子を変異させる。遺伝子編集などの精密育種技術により、農薬や肥料の少ない作物生産など、有益な形質を持つ動植物品種を効率的かつ正確な方法で開発できるとしている。これにより、英国の食料システムの持続可能性、レジリエンス、生産性を向上させるねらいだ。
2022年06月01日の日本貿易機構JETORO『英政府、農業食品の遺伝子編集研究促進に向け法案提出(英国)』https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/aa7c017c4b22c088.html
『遺伝子編集?』
なんだか遺伝子組み換え技術とは異なる技術のようです。
遺伝子編集について検索してみますと、どうやら『ゲノム編集』のことだそうです。
これこそが今注目されている新しい技術です。
- ゲノム:生物の遺伝情報全てを指す
- ゲノム編集:ゲノムを構成する物質DNAに少し人の手を加えた後、DNAがもつ元からある性質を自身で変えること
ちょっと分かりにくいので、もう少し分かりやすく言いますと、
「ゲノム編集は、手を加えた後は自分自身で変わってもらう(変異してもらう)こと」
と言った方が良いかもしれません。
となると、「蒸留作物」は遺伝子組み換え技術とゲノム編集技術の間に位置すること
になります。
遺伝子工学の問題
ただでさえ遺伝子組み換え作物はよくないという意見が見られるというのに、よくこういう「蒸留作物」を許可したなと思って読んでいたのですが、読み進めていくうちにやっぱり
否定的な意見をもつ登場人物もいました。
なぜなら「遺伝子組み換え技術」「蒸留作物」「ゲノム編集」、これら3つは人の手が加えられているため、それぞれ倫理的な面、生物的な面などから疑問視する人もいるからです。
もともと遺伝子工学は、「作物の収量を上げる」「農薬にも耐えられるようにする」ことを目的としていますが、生態系に影響を与えたり、人が食べても安全なのかどうかという意味で否定的な声もあります。
『GeneMapper-full build-』は、SF視点で食の安全・供給について考えさせてくれる
ものだと思います。
ただ、個人的には良いのか悪いのかと問われると判断に困りますね。
まとめ
農業×SF、なかなか新鮮でした。
現在の遺伝子組み換え技術・ゲノム編集に関して賛否両論あり、未だに終止符が打たれる
気配を感じません。
藤井太洋『GeneMapper-full build-』を読んでも賛否両論あることが分かります。
結局、問題が起きた時にどう対処すべきなのかということが大事なのかもしれません。
この作品は、日本の農業の未来について考えるきっかけにもなるでしょう。
もし気になった方がいらっしゃいましたらぜひご一読ください。
それでは、またお会いしましょう!