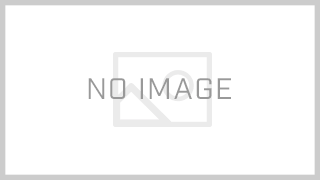変わった小説を読みたいのでしたら、この作品が取りあげられるかもしれません。
本作品は、文字が物語を形作る奇妙で魅力的な世界が描かれています。
日本文学の中でも『文字渦』は、言葉・文字とその先にある意味を考えさせるユニークで深いSF作品です。
本記事では、作品の魅力を紐解きながら、その斬新な構成やテーマに触れていきます。
『文字渦』のあらすじ
本作品は「文字」をテーマにした連作短編集です。
どの話を見ても、「文字」たちが規則に従わずに活き活きとしている様子が見られます。
例えば、分子生物学と関わる文字の話、文字同士で戦う話、文字が殺される話、文字だけでできた島の話など。
と、初めて読む方は何を言っているのか理解できないかもしれません。
(ライターとして、文字に触れている私にも当初理解出来ませんでした……。)
ところが読み進めていくと、文字が意思をもっているような感覚に囚われてしまいます。
『文字渦』の注目すべき点
普段何気なく読んでいる本でも、文字についてじっくり考えながら読む方はどれくらいいるのでしょうか?
おそらく本作品で文字について改めて考えてみたくなるかもしれません。
- 文字とは何か
- 文字・言語はどのようにして生まれたか
今回は、上記の2点に触れながら作品を紹介していきます。
文字とは何か?
表題作である「文字渦」に登場する人物「俑」。
この俑は、文字に対する興味深い観念を読者に提供しています。
俑にとっての文字とは、 一文字一文字が神聖を帯び、奇瑞を記し、凶兆を知り、天を動かすためのものである。
出典:『文字渦』- 円城塔 – (新潮文庫:2021年)
「文字」自体が、人間にとって神々しさをもつことを伝えています。
個人的に文字は、情報の一部・記号としか見ておらず深く考えてはいませんでした。
小説内の変わった設定としてとらえていましたが、2023年11月号に日経サイエンスで文字・言語に関する興味深い記事が載りました。
それは、インドの近くのベンガル湾に位置するアンダマン諸島に住む先住民について書かれた記事で、彼らが使用する言語がどのようにして生まれたのか記されている記事でした。
このアンダマン諸島の先住民が使用する言語一つ一つは、自身の体を通して周りの環境を認識した時に生まれるそうです。
文字ではなく言語の話になるため、少しずれた話なのではないかと感じる人もいるでしょう。
されど、『文字渦』で語られている発言と繋がっているように見えます。
大アンダマンの言語がどのように構成されているのか、以下のように書かれていました。
「自由語」と「拘束語」という2種類の語で構成されている。 自由語は全て名詞で、 環境とそこに生息するものを指し示す。一例は「豚」を意味するraで、単独でも使われる。 一方の拘束語は、 名詞や動詞、形容詞、副詞となる語で、他の物体が出来事、状態との関連を示す標識と常に組み合わせて使われる。
出典:日経サイエンス2023年11月号『大アンダマン語族 消えゆく言語が秘める世界観』
人間の体の部位や人間以外の動物、自然環境。
これらの単語は、先住民が相互に関係しあうことで生み出されるそうです。
まるで、言語・文字を生む古代人を見ているような気になります。
「文字渦」では、文字自体が世界を動かすような存在だと書かれているため、
大アンダマンの言語とニュアンスが異なりますが、文字・言語が世界と繋がっている点で
共通していると言えます。
強引かもしれませんが。
あながち、「文字渦」で俑が語っていた発言も変な話ではないのかもしれません。
文字・言語はどのようにして生まれたか
『文字渦』には、全部で12もの短編が収録されています。
そのうちの一つ「梅枝」にまた興味深い一文が書かれていました。
すなわち、境部さんにいわせるならば、テキストデータそれ自体は本ではない。 どう実体化させるかによって文章の性質は変わるといい、内容が変わることだって珍しくはない。
出典:『文字渦』「梅枝」- 円城塔 – (新潮文庫:2021年)
「境部さん」は、「梅枝」に出てくる登場人物です。
「梅枝」の話もかなりぶっ飛んだ話ではありますが、この「境部さん」の発言は意外に正しいことなのかもしれません。
深読みかもしれませんが。
なぜそう感じたのか理由を述べますと、上記の引用文に関わる興味深い記事を思い出したからです。
言語はいくつかの能力からなるプラットフォームから生じ,その一部は他の動物も持っているようだ。興味深いことに,人間の言語の複雑さは文化から生まれるらしい。話し言葉が多くの世代にわたって繰り返し伝えられることで,複雑になっていく。
出典:日経サイエンス 2018年12月号『特集:新・人類学 第1部 人間性の起源
高度な言語が生まれた理由』
複雑な言語は文化が絡み合う、つまり人間が関わってくることで生まれてくると書かれています。
時間の変容と共に、ある言語が本来の意味とは異なった形で使用されたり、新しい意味が付加されたりする。
ただ文章や言語を含んだデータを集めただけで、誰かが取捨選択したり、吟味したりしなければ、知識を蓄えただけの変化のない代物でしかありません。
また、脳科学の観点から言語がどのように生まれたのか説明している話も見受けられました。
動物の運動の組み立て・制御の脳機能と言語機能との類似性を考えると、大脳皮質の増大、発生期間の進化、言葉による情報伝達の有用性からくる社会的淘汰圧等に伴い、容量が増大した大脳必須の一部が言語音声処理に特化し、コードの運動制御機能の仕組みが音声処理に適用されて言語が生まれた
出典:『脳はいかにして言語を生みだすか』 – 武田暁、猪苗代盛、三宅章吾– (講談社:2012年)
上記の文からでも、「社会的淘汰圧等に伴い」と記されており、文化と同等かそれ以上の何かしらの変化が、言語を生む誘因となったと理解できます。
「梅枝」から引用した文は、そんな意味を含んでいないのかもしれませんが、一読者としてそう読み取りました。
『文字渦』補足
今回は、「文字渦」と「梅枝」の2話だけしか触れてきませんでしたが、他の10話も何か文字に関わる深い意味が隠されているかもしれないですね。
とここまで読んでみて、勘の鋭い方でしたら中島敦の『文字禍』のパロディか
と気づくかもしれません。
実は文字をテーマ、もしくは作品内で文字・言語に特徴のあるSF作品は他にも見られます。
- 筒井康隆『残像に口紅を』『虚人たち』
- 伊藤計劃『虐殺器官』
- ジョージ・オーヴェル『1984年』
- アンソニー・バージェス『時仕じかけのオレンジ』
- ダニエル・キイス『アルジャーノンに花束を』
- アルフレッド・ベスタ―『ゴーレム100』
そうなると、「ひょっとして中島敦の『文字禍』もSFになるのでは」と言えますね。
(あくまで主観なため、異論は認めます。)
いずれにせよ、SF作家にとって文字・言語は魅力的な代物なのでしょう。
日常で使用する何気ない代物。
しかし、一見何気ない代物が新たな発見へと誘う役割をもっているのかもしれません。